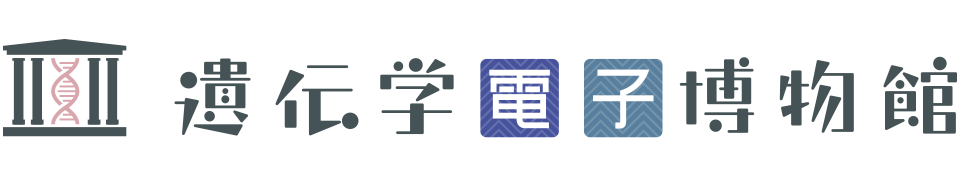- 農作物としてのイネ
イネは我が国のみならず世界の主要穀物のひとつです。人類の約半数が米を主食にしているとも言われています。人間とイネの付き合いは非常に古く、約1万年前までには中国で栽培されていたとされます。日本では、縄文時代に稲作文化が大陸よりもたらされました。その後、農家の品種改良に対する不断の努力、すなわち「育種」により、収量の増加、食味の向上、耐病虫性の付与、など多くの農業上の課題を克服する品種が、交雑育種によって作り出されてきました。
野生のイネは湿地に分布することが多く、栽培イネもまた、田んぼのような湛水条件でよく生育します。畑でとれる作物と比較して、除草の手間が少ない、土壌の流出が少ない、連作ができる、などの利点があります。それに加えて、地下水の供給源としての貯水効果もあると言われています。
近年、日本では減反政策や宅地への転換により、身近な田んぼがどんどんと失われています。しかし、日本の気候に最も適している穀物がイネであるのは間違いありません。穀物自給率が年々低下する一方、輸入穀類がどんどん値上がりする状況を考えると、稲作文化を、今一度見直す必要があるのではないでしょうか。- イネのゲノム解読と波及効果
2002年12月に、日本を中心とする国際コンソーシアムが、イネ全ゲノム塩基配列解読宣言を行いました。植物では、シロイヌナズナに続く2番目の全ゲノム解読となりました。栽培イネ(Oryza sativa L.)のゲノムサイズ(約3億9千万塩基対)は、シロイヌナズナの約3倍、ヒトの約8分の1です。イネゲノム情報から、イネの遺伝子は約3万2千個あると推定されています。タンパク質の直接的な設計図(mRNA)の配列を反映する完全長cDNA配列も、30,000個以上解読され、イネゲノム情報と併せて誰もがその情報を閲覧できるデータベースが構築されています。イネゲノム解読は、日本国が主体となって成功した初めてのゲノムプロジェクトとして、国内外から高く評価されています。
イネのゲノムサイズは、遺伝学的によく研究されているイネ科穀類(コムギ、トウモロコシなど)の中では最小です。また、イネ科作物のゲノム上での遺伝子の配置や構造は共通点が多いことが知られています。そのため、イネ科穀物の遺伝子研究ではイネゲノム情報が広く用いられています。イネのゲノム情報は、他のイネ科作物の遺伝子研究に多大なる波及効果をもたらしたのです。- イネの遺伝子研究
イネの遺伝子研究は、育種研究の一部として古くより行われ、その根幹を為す技術である人工交配法は明治37年(1904年)に確立されました。しかし、現在の分子生物学としての歴史は浅く、1989年に日本の研究者が世界で最初にイネの組み換え植物の作成に成功したのが一つの契機となりました。その後、やはり日本の研究者によって、土壌細菌アグロバクテリウムを介したイネへの遺伝子導入法が確立され、現在では誰にでも簡単にできる技術となっています。
イネの遺伝子を同定する方法のひとつに、突然変異の利用が挙げられます。突然変異は、化学変異源処理や放射線の照射、細胞培養による刺激、などにより引き起こされるゲノム中のDNA配列や遺伝子構造の変化が原因です。イネでは、受精後間もない卵を持つ頴花を化学変異源メチルニトロソウレア(MNU)の水溶液に浸すことで、均一な突然変異体を作成する方法が確立され、広く遺伝子研究に用いられています。近年では、通常はイネゲノム中で眠っており、細胞培養刺激によって自分自身のコピーをゲノム中に増殖させることのできるTos17配列(レトロトランスポゾン)が存在することが明らかとなりました。Tos17配列が転移した先の遺伝子を破壊する現象を利用して、これまでに1万を超える突然変異系統が作出されています。Tos17配列を利用して、破壊された遺伝子の構造や機能を調べることができるため、イネの遺伝子研究は格段に飛躍しました。なお、これらの突然変異体は外部遺伝子を導入する遺伝子組み換え植物とは全く異なるものなので、野外での大規模な展開にも全く支障はありません。
突然変異と対極をなすものとして、自然突然変異が挙げられます。イネで最初に単離された遺伝子は、白葉枯病抵抗性遺伝子Xa21です。多くの白葉枯病抵抗性は、在来品種が元々もっている自然変異のひとつです。遺伝子単離をXa21を例にして説明すると、白葉枯病菌に対して強いイネ品種と弱い品種を交雑し、その後代で遺伝学的な解析を行います。親品種で多型を示すDNAマーカーを利用して抵抗性遺伝子のゲノム上の位置を絞り込んでいくこの方法をマップベースクローニング法、あるいはポジショナルクローニング法といいます。また、多くの農業形質は、量的遺伝子と呼ばれる複数の遺伝子座(QTL)によって支配されています。最初に人類遺伝学で提唱された方法を利用したQTL解析によるイネ遺伝子単離も普遍的に行われています。これの方法により、耐病虫抵抗性、矮性、出穂性など農業上重要な形質を司る多くの遺伝子が次々と単離されています。- イネの遺伝子研究を支える遺伝子資源
イネ属は、2種の栽培イネおよび約20種の野生イネで構成されています。遺伝学研究所は、世界でも有数の野生イネコレクションを有しています。その数はおよそ1,700系統あり、ほぼ全てのイネ属野生種を含んでいます。在来栽培イネ品種も合わせると、その保存総数は約6,000系統にもなります。それの収集は、1960年代から始められ、現在では原産地の環境破壊により、現地ですら見つけることのできない野生イネなども含まれていますので、今後その価値は益々高まると思われます。
遺伝子資源の重要性を、耐虫性遺伝子を例にとって考えてみましょう。イネの茎を吸汁する害虫として知られるウンカは、東南アジアからジェット気流に乗って日本に飛来するといわれています。どんなに抵抗性の高い改良品種を投入しても、数年も経てばウンカ側の遺伝子が変化し、その品種を食害できる生態型(バイオタイプ)のウンカが現れることが知られています。まさに、害虫と育種家との間のいたちごっこの様相を呈しています。従来の品種改良は、その抵抗性遺伝子の素材を在来の栽培品種に求めていましたが、在来種に含まれる抵抗性遺伝子の種類には限界があります。そこで近年、対象を野生イネに拡大する動きが本格化しています。事実、在来品種には無いタイプの抵抗性遺伝子を野生イネが持っているケースが報告されています。
現在、文部科学省主導によるナショナルバイオリソースプロジェクトの下、イネを含む多くの生物で、多様な遺伝子資源を永続的に保存し、研究や品種改良などに利用していくための体制作りが模索されています。生物の持つ遺伝的多様性は、それぞれの種が長年に亘ってそれぞれの生育環境に適応してきた結果であり、それらを人間が実験室で再現するのは現時点ではほぼ不可能です。また、将来的にどのような遺伝子が有用になるかは誰にも判らないので、近視眼的に不要だからといってむやみに遺伝子資源を取捨選択する行為は慎むべきです。生物資源は、人類共通の財産として守り育てながら、有効に利用していくべきものと考えます。- もっと詳しく知りたい方へ
-
遺伝研で行われているイネの基礎研究