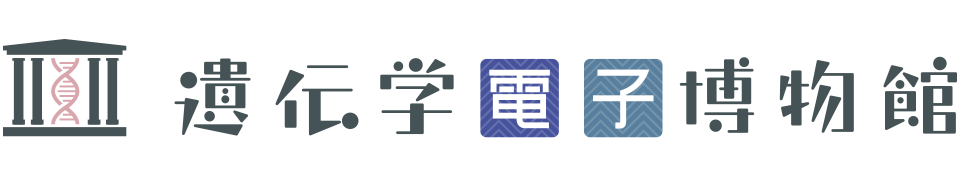高等動植物を始めとする有性生殖を営むほとんどすべての真核生物 (eukaryote)では、体を構成する細胞は、生物の種によって決った染色体 (chromosome)のセット(これをゲノムという)を2セットずつもっている。このような二倍体(diploid)染色体をもつ生物は生殖のときに、減数分裂(meiosis)によってこのゲノムが1セットずつ生殖細胞に分配され、生殖細胞では精子も卵も染色体数は半減して半数体(haploid)となる。このような生殖細胞が受精すると、精子と卵の染色体が合一して再び2セットのゲノムをもつ受精卵となり、それが発生して二倍体の生物に発育する。
「基礎遺伝学」(黒田行昭著:近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載
- 伴性遺伝
このような有性生殖をする生物の二倍体染色体の中で、2セットのゲノムの各ゲノム当り1本の染色体は雄と雌とでその組合せが異なり、これを性染色体(sex chromosome)という。他の染色体はすべて常染色体 (autosome)といわれ、雄でも雌でも同じ形と大きさの染色体が同じ数だけ存在する。常染色体上に存在する遺伝子は、すべてメンデルの法則にしたがって遺伝する。しかし性染色体上の遺伝子は雄と雌とで伝わり方が異なり、これを伴性遺伝(sex-linked inheritance)という。
ヒトでは性染色体が、女性ではゲノム当り1本ずつのXがあり、体細胞では性染色体の構成はXXである。男性はXをもつゲノムとYをもつゲノムがあり、体細胞では性染色体構成がXYとなっている。ヒトの色盲の遺伝子はX染色体上にあって、劣性である。女性ではX染色体が2本あるので、その中の1本が正常の遺伝子をもっていれば、他の1本のX染色体に色盲の遺伝子があっても見かけは正常となる。これに対して男性ではX染色体が1本しかなく、Y染色体は活性がないので、この1本のX染色体に色盲の遺伝子があれば劣性でも色盲となって現れる。
伴性遺伝では、このようにその遺伝子が母親にあるか、父親にあるかによって、その子への遺伝子の伝わり方が異なり、また子での現れ方が女子と男子とで異なる。父親が色盲であっても母親が正常であれば、その子は男女とも正常であるが、母親が色盲であれば、父親が正常であっても、女の子は見かけはすべて正常、男の子はすべて色盲になる。「基礎遺伝学」(黒田行昭著:近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載
- 同義遺伝子
生物の同じ形質を支配する2対以上の対立遺伝子があって、しかも、そのいずれか一つの遺伝子が優性であれば、優性の形質を示す遺伝現象がある。このような遺伝子を同義遺伝子(multiple genes)という。
ナズナ(俗にペンペングサと呼ばれる)のサヤには、普通に見られる三味線型(ウチワ型)をしているものと、細いヤリ型をしているものがあり、三味線型とヤリ型とを交配すると、雑種第一代(F1)ではすべて三味線型となる。F1どうしを交配するとF2では三味線型とヤリ型とが15:1の比に分離する。この現象も一見、メンデルの法則に当てはまらないように見えるが、実はこれもメンデルの法則に従っている。三味線型を支配するのは二つの優性遺伝子CとDで、その中のどちらか一つあれば、他の遺伝子がすべて劣性でも三味線型となる。そしてこの優性遺伝子が一つもないもの(ccdd)のみがヤリ型となる。すなわち、メンデルの法則の9+3+3=15がすべて三味線型となる。「基礎遺伝学」(黒田行昭著:近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載
- 母性遺伝
細胞核内の染色体上にある遺伝子は、メンデルの法則に従って生殖細胞を通じて子孫に伝えられる。また母親の細胞の細胞質は卵を通じて子に伝わる。しかし父親の細胞の細胞質は、受精の際、精子の核のみが卵に入り、子には伝わらない。
核内の遺伝子によって産生された物質が細胞質に貯えられ、それが母親の卵を通じて子に伝わり、子の形質として現れてくるものが知られている。このような遺伝を母性遺伝(maternal inheritance)という。母性遺伝の例としては、カイコの卵の越年性(正常卵)と不越年性(褐色卵)があり、越年性(遺伝子型++)は不越年性(bw/bw)に対して優性であるが、F1の卵は父親の越年性、不越年性に関係なく、母親のもっている遺伝子型によって支配される。つまり母親のもっている遺伝子型が次世代の卵の細胞質を通じて発現される現象である。「基礎遺伝学」(黒田行昭著;近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載
- 致死遺伝子
遺伝子は生物の発生から死ぬまでのある特定の時期に、体の中のある特定の細胞や組織、器官にその作用を現し、その遺伝子特有の酵素やタンパク質を形成し、それが生物のきめられた場所の形や色、大きさとなって現れるものが多い。しかし、遺伝子の中には突然変異を起して、その作用が異常になると、生物の生存や発育ができなくなり、その個体に死をもたらすものがある。
マウスやショウジョウバエなどで、このような遺伝子が数多く知られていて、致死遺伝子(lethal gene)という。図1・5はマウスの致死遺伝子がマウスの正常発生のどの時期に、どのような組織、器官に異常を現し、個体を死に至らせるかを示している。
致死遺伝子の多くは優性の形質を支配する遺伝子で、ヘテロの状態で体のある部分に異常が現れ、致死作用は劣性として作用するので、ホモの状態になって始めて個体を死に至らせる。ヒトの胎児の流産した個体などで、この致死遺伝子によるものが多いと考えられている。「基礎遺伝学」(黒田行昭著;近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載