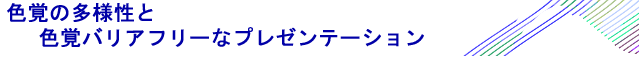
| 第3回 すべての人に見やすくするためには、どのように配慮すればよいか |
| ■著者:岡部正隆 Masataka Okabe / 伊藤啓 Kei Ito / ■著者プロフィール |
|
はじめに カラー印刷技術の発達やパソコン、インターネットの普及によって、論文や学会発表、ホームページなどでカラフルな色彩を用いた情報発信が誰でも容易にできるようになった。しかし読者や聴衆の色覚には、遺伝的背景の違いや, 眼のレンズや視細胞などに障害を与える疾患によって、大きな個人差が存在する。色を使って重要な情報を伝えようとするときに、このような色覚の多様性のために情報が相手に正確に伝わらない危険があることは、十分に認識されているとは言えない。 第1回、第2回の連載を通じて、色覚がいかに多様であるか、色盲*1 の人がどのような色を見ているのか、さらに色覚の多様性がコミュニケーションをどのように難しくしているかについて紹介した。誰でも同じ色を同じように知覚しているのであれば、文字や記号と同じように色を絶対的な表現として情報伝達に用いることが可能であろう。しかし、すべての人が色を同じように知覚することができない以上、正確に情報を伝えるための絶対的な表現として任意の色を用いることは困難である。 一方、目の前の複数の情報を素早く見分けて互いに関連しているか異なっているかを一瞬に判断できる点では、色の塗り分けは極めて有効である。色盲の人と色盲でない人は、すべての色を異なって知覚しているわけではなく、同じように判断できる色の組み合わせも多数存在する。誰にでも見分けやすい色の組み合わせを選び、さらに文字や記号、線の形状やハッチングなどの形態の差異を用いて色なしでも十分に理解できるようにプレゼンテーションを設計することで、色を用いた情報伝達のメリットを利用しつつ、色だけを用いた場合の情報伝達の失敗を防ぐことができる。 連載最終回では、まず色盲の「治療」や「矯正」がいかに困難で事実上不可能であるかを解説し、次に読者や聴衆の色覚が多様であることを前提とした色覚バリアフリーなプレゼンテーションの重要性と、その具体的な方法論を紹介する。 |
- 先天色盲を “治療” “矯正” する各種の方法
- 色盲お助けグッズ
- 色盲の人の側が対応するのに必要なコストと色覚バリアフリー化に必要なコスト
- 蛍光染色画像や DNA アレイの画像などデジタル情報の表示
- グラフや概念図 (スキーム) などの図版
- 見分けやすい色の選択
- 学会でのスライドや PowerPoint,ポスター,さらにホームページのデザイン
- 学会などで発表する際の留意点
- 講義や授業に際して注意すべき点
- おわりに
| *1 「色盲」については差別的表現を避ける意図から「色覚異常」「色覚障害」「色弱」などと言い換えられることも多いが、本稿では、「異常」などの無用な価値判断を含まず、バリアフリーにおいて最も配慮が必要な重い症状までも包含している「色盲」という用語に統一する。言葉の抱える問題に関しては、本連載第1回の註*1 やホームページ http://www.nig.ac.jp/color/ を参照されたい。 |

このマークに関してはここをクリック! |
細胞工学Vol.21 No.9 2002年9月号[色覚の多様性と色覚バリアフリーなプレゼンテーション]
・文章に関しては、秀潤社と著者に著作権がございます。