
| 第3回 すべての人に見やすくするためには、どのように配慮すればよいか |
おわりに
本連載は 3回にわたって、色覚のメカニズム、先天色盲と後天色盲の原因、色覚のタイプによる色の見え方の違い、色の定量的表現、色盲の治療や矯正などについて解説した。最後に多様な色覚に対応したバリアフリープレゼンテーション法を紹介し、図22 に重要なポイントをまとめた。
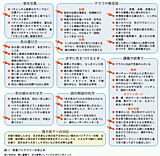
|
| 図22. 色覚バリアフリーのまとめ |
多くの人は普段意識していないが、色に情報を載せて他人とコミュニケーションするには、誰が見てもその色が同じように見えることが前提になっている。しかし色覚特性が大きく異なる色盲の人がこれだけ高い頻度で存在し、色盲でない人にも色覚には大きな個人差が存在するうえ、加齢に伴って色覚はさらに変化する。多数派の色覚に対応してカテゴリー化された「色名」は、色覚のタイプが異なる人には色との対応が難しい。このように色は文字や記号のように絶対的な指標としては、コミュニケーションに使うことはできない。
とはいえ生物の長い進化の過程で培われてきた色による情報の読み取りは、情報を瞬時に把握するためには非常に便利なキーである。たいていの色を見分けている色盲の人にとっても、これは同じであることに注意したい。色覚バリアフリーにするということは、色を使わず白黒にするということでは決してない。多様な色覚に対応した、上手な色の使い方をすることである。
今回紹介した色盲の人にも見分けやすい「バリアフリーカラーパレット」 (図19) を活用し、さらに色だけに頼らず、色以外の方法 (文字や記号、形状の違いなど) を必ず併用して冗長的に情報を発信することで、色を用いたコミュニケーションのデメリットを避け、メリットだけを活かせるようになる。ぜひご協力をお願いしたい。
学校の健康診断で色覚検査が廃止され、遺伝に関する授業も減ってしまうことで、色覚に多様性があることを人々が知るチャンスは今よりも少なくなるかもしれない。だがむしろ、色覚に多様性があることは、血液にいろいろな型があるのと同じような当然の常識として、多くの人に認識されるべきである。A型糖鎖抗原や B型糖鎖抗原への凝集能力を欠いた O型の血液型の人や、他より人数が少ない AB型の人は、「血液異常」であるわけではない。同様に多様な色覚も、人数の大小で「正常」と「異常」に区別されるものではなく、単なる遺伝的多型 (ポリモルフィズム) であるという認識が大切である。
20世紀における色盲の歴史は、21世紀のゲノム時代における科学者の責務に対し、大きな教訓を与えてくれる。色盲の人は他の人と色の見え方が異なるという知識はダルトンの時代からあったが、実際にどの人が色盲であるかを判別するのは難しかった。したがって色盲の人でも努力したり色のセンスが優れていれば色を扱う職業にも自由に就くことができ、色盲でない人でも色に関する注意深さやセンスが劣っていれば、そのような職業には就けなかった。実力による勝負が成立していたわけである。
しかし状況は石原表の出現で一変する。簡単な検査で正確に色覚を判定できるようになると、進路指導、入試、就職などで、安易に色盲の人を排除する風潮がすぐに出てきた。その職業の適性に他の様々な、より重要な要素が多数あるにもかかわらず、簡単かつ確実に検査できる色盲についてだけ、「万が一もしかしたら、○○のような状況では色盲の人は対応できないかもしれない」というような非常に稀な状況に対する科学的検証を欠いた憶測で、一律な排除を合理化してきた例が非常に多い。
このように
簡単確実な検査法が確立する
↓
「万が一」を考えて安易に過剰な排除体制を取る
という図式は、残念ながら今も多く繰り返されている。遺伝病の保因者であるかどうかが診断できるようになったとたん、その人たちが保険に入れなくなる例などは、現代の日本でも現実に起きている。
人間は元来非常に多様であり、その多様性を認めて誰もが同じように幸福に暮らせる手段を提供することが科学の責務である。しかし科学の進歩によって従来見つけることができなかった多様性を見つけられるようになると、その一部を「正常」、残りを「異常」と判定して後者に不利益を与えるという差別構造に、現代科学は知らず知らずのうちに加担してきてしまっている。色盲においては、我々科学者(特に医学関係者)が親切なヒントのつもりで何気なく口にし、解説記事等に書いてきた、「こういうものが見分けられない可能性がある」という推測が、すべて一般の人には「権威ある専門家の確定的な助言」として受け取られ、過剰排除の科学的根拠として利用されてきたという構図がある。しかし科学者には、自分たちの発言が社会に対してそれだけの権威と効果を持ち、結果として差別を惹き起こしたという当事者意識が非常に薄い。一部の献身的な例外を除いては医師の視野は症状の改善や進路指導など患者個人のレベルに限られがちであり、社会に対するきちんとした啓蒙活動をして過剰排除や差別の構造にメスを入れることが、自分たちにしかできない使命であるという認識が十分ではない。
我々科学者の日々の努力によって、人間の様々な特性を左右する遺伝子を簡単確実に検査できる時代が迫っている。生活にさしたる支障のない色盲などのレベルではなく、寿命の長短、癌などの病気の発症しやすさ、精神疾患のかかりやすさなど、これまで意識されていなかった無数の「遺伝子異常」「突然変異」が、遺伝子検査で検出可能になることが予想される。だが人間は、「何かネタさえあれば、ことあるごとに正常と異常に分けて一方を差別したがる」という哀しい生物でもある。色盲ですらこれだけの差別につながったのだから、今後続々と登場するであろう遺伝子検査によって「早死にしやすいかもしれない」とか「精神病になりやすいかもしれない」と「科学的に」判定された人がどのような差別を受け、不利益を被るかは、想像に難くない。科学者が自己の言動が社会に与える効果を真剣に見直し、たとえ善意の助言のつもりであっても差別形成に加担しかねない危険を認識し、結果として生じうる差別構造に対する当事者意識と責任感を持たない限り、せっかく実用化した遺伝子検査がオーダーメード医療の実現や社会のバリアフリー対応の改善でなく、安易に「少数派を異常だと定義し」、「検査で選別・排除し」、「選別された本人に人生の選択肢が狭いことを納得するよう迫る」ためばかりに使われる可能性は、残念ながらかなり高い。
様々な状況から推測すると、石原忍博士は色覚検査表を差別に使うために作成したわけではないらしい。しかし結果として石原表による検査は多くの色盲の人の将来を閉ざし、日本だけでなく世界中で怨嗟の的になってきた。意図が純粋ならば後世の人から怨嗟の対象にはならない、ということはないということである。我々が人類の幸福を願って現在進めているはずのゲノム研究の成果を、数十年後に同じような怨嗟の対象にさせないためには、20世紀における色盲差別の歴史と21 世紀におけるバリアフリー化の努力は、貴重な教訓と試金石になるに違いない。
エレベーターを設置したり、道路の段差をなくしたり、点字ブロックを設置するといった他のバリアフリーと異なり、色覚バリアフリーは行政が行う社会基盤の整備を待っていれば進むという性質のものではない。色を用いた日々のコミュニケーション自体がバリアフリーの対象であり、この社会に生きるすべての人が当事者なのである。この点からは、色覚バリアフリーの推進における最大の障害は、「これまで見慣れたもの、やり慣れた習慣をあまり変えたくない」という素朴な感情かもしれない。実際に、赤と緑の蛍光染色画像をマゼンタと緑に変えた方がよいという提案に対し、「でも何となく見慣れてない変な色遣いだ。赤と緑のほうが目に馴染んでいてよい」という反応を受けることは少なくない。だが、現実に困っている人がいることを知ったうえでこれまでの慣例をあえて続けることは、単なる消極的な反応というには済まされない側面もある。社会基盤を整備するということは、役所や制度が対応することを待つことではなく、普通の人一人一人がバリアの存在を認識し、それを除くような行動を、自分ができることから実践してゆくことなのである。
謝辞
本稿を執筆するにあたり、東京慈恵会医科大学の北原健二、大城戸真喜子、滋賀医科大学の山出新一、宝仙学園短期大学の市原恭代、(株)タムスの田中陽介の各氏から多大な御助言をいただきました。国立遺伝学研究所の山尾文明、吉森保、山田琢磨、岡崎国立共同研究機構生理学研究所の鯉田孝和、大阪大学の藤田一郎、京都大学の三上章允、 Medical College of Wisconsin のJay Neitz の各氏からは貴重な情報やコメントをいただきました。国立遺伝学研究所の池尾一穂、白木岐奈、林茂生(現理化学研究所)の各氏、オリンパスプロマーケティング(株)の薮内正和、(株)北計工業の橋爪慎哉、(株)文化総合研究所の橋本知子、木村麻樹の各氏からは画像や図版を提供していただきました。また、アドビシステムズ(株)、オリンパスプロマーケティング(株)、カールツァイス(株)、(株)ニコンインステック、日本バイオ・ラッドラボラトリーズ(株)、ライカマイクロシステムズ(株)の各社から情報提供していただきました。この場を借りて感謝申し上げます。
文献
- 今村勤:日本眼科紀要(1962) 13: 611-616
- 今村勤:臨床眼科(1975) 29: 119-125
- Okajima K, et al: 9th Congress of the International Colour Association, Proceedings of SPIE (2002) 4421: 256-262
- Ichihara YG:Internet Imaging (2001) 4311: 419-426
・文章に関しては、秀潤社と著者に著作権がございます。